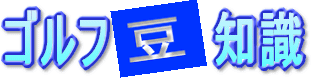
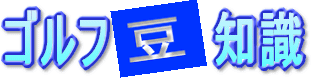
球面上のえくぼ(ディンプル)
ゴルフボールの表面にある多数の小さなクボミを指します。本来は、頬にできるえくぼの意味。
天然ゴムのワンピースボールの全盛時代、表面がつるつるしたニューボールより、使って表面に無数の傷がついたボールのほうがよく飛ぶという、不思議な事実が経験的に知られています。
そこから、人為的な窪みをつけるようになり、ボールの飛びの研究が始まりました。1890年頃には、丸い突起の逆ディンプル=ピンブル(にきび)が考案され、形状が似ていることから、ブランブル(木いちご)と呼ばれるようなボールが出現しました。これは大きな空気抵抗の割りには質量不足で、そんなに飛びませんでした。
そして、1899年、堅く重い芯に糸を巻いたボールが発明されると、今度はこの表面を改善する研究が行われ、英国ダンロップ社が1910年、今のようなディンプル状のボールを開発しました。その後ディンプルの断面の形状やその数の研究がすすみ、今日のボールに至っています。